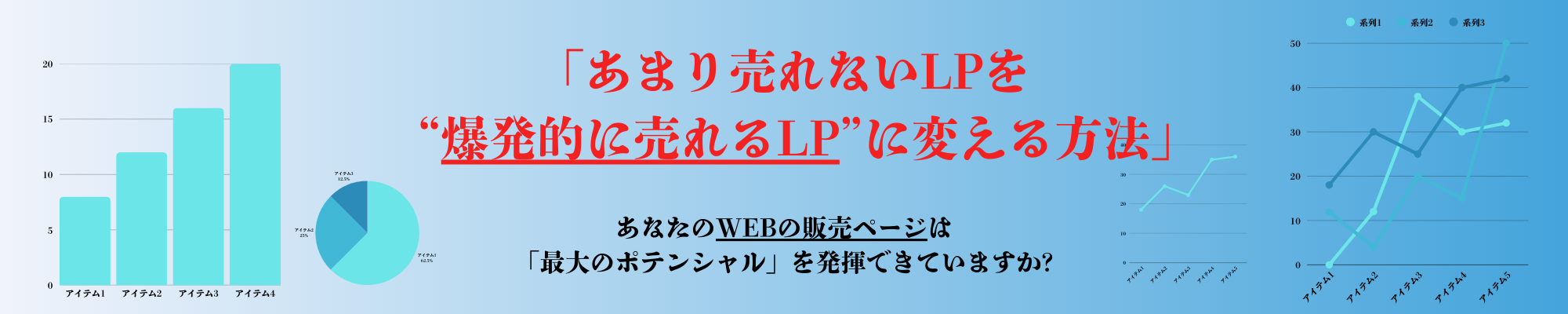世の中には、無数の広告がひしめいています。
数多くの商品やサービスが存在し、
それぞれに多くのライバルがいる以上、当然といえますね。
ただ、そのうちのどれほどの広告が
「真に売れる広告」といえるでしょうか?
私は、ほとんどが「あまり売れない広告」だと
思っています。
もちろん、各企業にしてみれば
「それなりに売れている」と言うかもしれません。
私の言う「あまり売れない広告」というのは、
「もっと売上を伸ばせる余地がある」という意味。
それなのに、広告を改善しないというのは、
非常にもったいないと言わざるをえません。
・・・
ではなぜ、世の中には
「売れない広告」がひしめているのでしょうか?
私は以下の2点が大きいと考えています。
- イメージコピーの影響
- コピー本の影響
まず、「イメージコピーの影響」から見ていきましょう。
イメージコピーというのは、
見た人に「何らかのイメージ」を与えることが目的のコピー。
新聞に掲載されている、短いキャッチコピーや、
テレビCMに流れているようなキャッチコピーですね。
こういったコピーは、
その場で商品やサービスを売ることを目的としていません。
企業イメージを上げたり、
あるいは、お店に行ったときに思い出してもらったりする。
そういったことを目的とするコピーです。
ですので、こういったコピーの「乗り」で
通販のLPを書いても、当然ですが売れません。
その場で商品(サービス)を売るコピーは、
DRM広告といわれますが、
イメージ広告はDRM広告ではないからです。
世の中のチラシや新聞広告、LPには、
その冒頭に「意味不明なキャッチコピー」が
掲げられていることがあります。
私は、これは「イメージコピー」を誤解して、
「売るためのコピー」に流用しているからではないか?
と見ています。
イメージコピーには具体性がありません。
抽象度が高いため、
その場で売るコピーとしては適さないのです。
・・・
「売れない広告」が多い、もうひとつの理由。
それは、私は「コピー本の影響」が強いのでは?
と考えています。
日本では、神田昌典氏が執筆したコピーライティング本が
販売されています。
こういった「日本人が書いたコピー本」は
よくまとまっていて、大変すばらしいのですが、
あくまで「分類」「型」にとどまっています。
実例にとぼしい傾向があるのです。
たしかに型に当てはめてコピーを書けば、
ある程度は売れるコピーができあがるでしょう。
しかし、コピーというのは、
そういった画一的なものではありません。
コピーというのは、あたかも
水彩画のようなものです。
つまり、描く(書く)本人が実践を積むなかでしか
スキルアップしないのです。
ですので、もしコピーライティングを学ぶのであれば、
実際に広告で成功している巨匠であるべきです。
そういった人たちは、
自身のコピーを公開していることが多いです。
たとえば、ジョセフ・シュガーマン。
彼の書いた『10倍売る人の文章術』は、
コピーライティングのバイブルと呼べるほどの著作です。
シュガーマン氏の書いたコピーも、
いくつか掲載されています。
・・・
ただ、ここにもうひとつの落とし穴があります。
シュガーマン氏の広告のヘッドラインは、
一見すると「気の利いたキャッチコピー」のように
見えることです。
そのように勘違いした日本人は、
「そうか。気の利いたキャッチコピーにすればいいのか」
と早とちりしてしまうことに…。
しかし、そうではないのです。
シュガーマン氏のコピーは、
ウォールストリート・ジャーナルという新聞をはじめ、
格式の高い雑誌に掲載されることが多かったのです。
そのため、広告のように見えない広告、
つまり「記事広告」をベースとしていました。
「なんだろう?」と思わせるような、
好奇心を誘発するようなキャッチコピー。
それによって、コピー本文を読ませるというのが、
シュガーマン氏の手法でした。
ですので、そういった「戦略」を知らずに、
キャッチコピーの形だけをまねても、
「売れない広告」しかできないのです。
もちろん、「好奇心をベースとした出だし」は、
DMやメルマガなど、特定の分野では有効です。
しかし、現在の日本の通販業界では、
「メリットを主体としたキャッチコピー」で始めることが
反応を取るための鉄則といえます。
WEB広告というのは、
雑誌や新聞に掲載するわけではないからです。
WEBというのは、気の散るような
いろいろなものが、次々と目に入ってきます。
また、ネットユーザーというのは、
オフラインよりも「気が短くなる」傾向にあります。
そういった環境では、
ダイレクトに「メリット」に訴求するような
キャッチコピーが求められるのです。
・・・
以上のように、
日本に「売れない広告」がひしめいている理由としては、
- イメージコピーの影響
- コピー本の影響
この2点が考えられるのです。